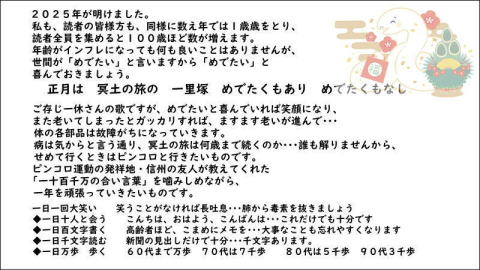てやんでぇ 第00回 蔦屋重三郎 Who?
作 文聞亭笑一
明けましておめでとうございます
昨年中は平安絵巻「紫が光る」でお騒がせしました
今年の江戸は・・・
蔦重を調べるほどに「面白いかも・・・」という雰囲気で
またまたお騒がせすることにしました
今年もよろしくお願い致します
クリックで拡大
さて、今年のNHK大河「べらぼう」ですが、江戸中期の庶民の町が舞台です。
中学、高校の歴史の授業では「この辺りは試験に出ないから飛ばす・・・」などと先生ですら「パス」した部分で馴染みがありません。
昨年の平安期もその意味では同様でしたから、二年続けて日本史上の「マイナー」な時代が舞台になります。
とはいえ、教科書に載るほどの事件がなかった時代とは「平和な時代」でもあります。
平和呆けしているという点では、現代に最も近い時代なのかも知れません。
「光る君へ」では最後の方に刀伊の入寇という外国からの侵略者の話がありましたが、今年の物語「べらぼう」も終盤の頃にはロシアによる蝦夷地侵略の話題が出てきそうです。
第1節 べらぼう と てやんでぇ
今年のタイトルですが、NHKが江戸言葉の「べらぼう」で来ましたから、同じく江戸言葉の「てやんでぇ」にしました。
どちらも江戸下町のイナセなアンチャン達が使う言葉です。
べらぼうめ・・・あほ、ばか、まぬけ の類いの言葉で、相手を軽蔑する響きがあります。
転じて「馬鹿げている」「程度が悪い」「常識外れ」などの意味でも使われます。
今回の主人公・蔦屋重三郎は江戸の出版業界に革命を起こしたとされますから「常識破り」という意味が強い命名かも知れません。
「べらぼうめ」と言われたら「てやんでぇ」と返します。
何を言うかバーカなどと言って反論します。
NHKが「べらぼうめ」・・・と言ってきたら「てやんでぇ」と返そうかと思います(笑)
第2節 蔦屋重三郎 Who?
恥ずかしながら文聞亭は歴史好きと言いながらも蔦屋重三郎という名をはじめて耳にしました。
いわゆる初耳でした。NHKの番組案内を見たり、Netで検索したりしましたが、もしかして現代のツタヤ書房のご先祖様かなどと勘違いしておりました。
ツタヤ書房とは関係ありません。
ただツタヤの創業者が蔦屋重三郎を尊敬していて、書店名をもらった、真似た、と言うことのようです。
江戸中期(9代将軍から11代将軍)の頃1770-1800年頃にかけて、江戸の出版界で活躍したのが蔦屋重三郎でした。
蔦重(略称)の初期は田沼意次の時代です。
そして終盤には松平定信の寛政の改革の嵐が吹き荒れます。
江戸文化の爛熟期と揺り戻し・・・と言った時代背景でしょうか。
白河の 清き水にも住みかねて 元の濁りの田沼恋しき
時代を現わす狂歌としては最高の出来とも言うべき一首ですね。
田沼政治とは・・・いわば自由化です。
武家社会の儒教的な倫理規定や、士農工商と商業を卑しめる発想を緩めて、商業資本からの税金で政治運営を行いました。
勢い・・・金権型政治になりがちでしたから、それを改めて保守政治に戻そうとしたのが松平定信です。
定信は白河藩主でしたから「白河の清き水」であり「沼田、泥田の濁り水」が田沼意次になります。
舞台は江戸の色町・吉原、公娼・売春街です。NHKはこの街をどう描くかですが、現代の銀座、柳橋、祇園、北新地などと同様な、料亭として使う社交街でもありました。
ヤクザも闊歩しています。あまり・・・清く、正しく、美しい町ではありません。