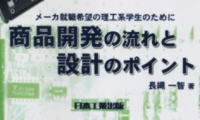大和魂(第43号)
文聞亭笑一
先般、尖閣列島を巡って日中の外交問題が発生しました。領土問題という国防の根幹にかかわる重大問題です。この問題について、内閣の対応を批判するつもりはありませんが、良く似た事件がこの物語の中でも発生しました。
海援隊の隊士が、長崎で英国人水兵を殺傷したという事件で、英国はこの事件を梃子(てこ)にして日本政府に賠償を求め、あわよくば日本侵略の糸口を作ろうという策略に出ます。
裁き方を間違えると…中国がアヘン戦争で侵略されたのと同様の手口ですから、勤皇と佐幕の争いが外国勢力に利用され、国を失う危機でもありました。
今回の尖閣列島の問題も、中国による故なき言いがかりです。違法操業し、かつまた警備船に体当たりしてきた漁船は、中国政府のあずかり知らぬ偶発事件でしょうが、これを、外交問題に利用しようとした中国政府の思惑は、幕末の英国と大差ないでしょうね。
日本政府が対応を間違えたら、それに乗じて領土問題の存在を既成事実化し、東シナ海の権益や、中国に進出している日本企業に圧力をかけようという狙いだったのでしょう。
「中国の国内問題を外国との紛争に転化して…云々」などとマスコミは解説していましたが、そんな生易しいものではないと思いますよ。
中国政府の覇権主義は、150年前のイギリスの植民地主義と同じで、したたかだと思いますね。隙あらば…いつでもつけこんできます。党の規定だからと、僅か3ヶ月の総理の椅子をめぐって、コップの中の嵐に興じていた日本が隙を見せたのです。
「学べば学ぶほどわかった」政府ですから、歴史にも学んで欲しいものです。
177、元々竜馬の大政奉還策というのは、一種の魔術姓を持っていた。討幕派にも佐幕派にも都合よく理解されることが出来る。たとえば後藤象二郎が理解したのは「徳川家のためにもなり天皇のためにもなる」という矛盾統一の案、ということであった。この点、勤王か佐幕かの矛盾に悩む山内容堂にとってはこれほどありがたい案はない。
一方、中岡のような倒幕急進派にとっても、大政奉還の気球を上げることによって、合法的に倒幕兵力を京に集中できるのである。
要するに、政治が持つ魔術性をこれほど見事に備えている案はないであろう。
竜馬の船中八策の提案には、武力討幕派の薩摩や中岡慎太郎が猛反対します。もう一押しで倒せる相手を救ってしまうではないか、大政奉還しても徳川家は400万石で、日本最大の藩として残ります。発言権という点で言えば薩摩の6倍、長州の11倍、土佐の17倍にもなります。薩長土が束になっても140万石弱ですから、遥かに及びません。
龍馬を全面的に信頼していた西郷吉之助ですら、「竜馬の裏切り」と捉えました。岩倉具視と倒幕の密議を繰り返している大久保一蔵などは「龍馬を斬れ」と口走る始末です。
盟友である陸援隊の中岡慎太郎も我が耳を疑います。「竜馬は後藤象二郎に取り込まれたか」と怒ります。
大政奉還とは、見かたによって二面性のある提案でしたが、竜馬の狙いはあくまでも無血革命にありました。日本人同志が戦うという愁嘆場(しゅうたんば)を避けたかったのです。京都に討幕派の兵力を集結し、天皇を中心とする新政府の旗を掲げ、強力な武器で武装した政府軍を組織すれば「抑止力」で諸大名を新政府に参加させられると目論んでいました。そうなれば、手足をもがれた徳川家も抵抗できずに枯れてしまうであろうという政治戦略です。時間は多少かかりますが、徳川家内部にいる勝海舟や、大久保一扇などの国際派、良識派が新政府への参加に導いてくれるだろうという期待がありました。
竜馬は、その良識派の一人、永井尚志の説得に出かけます。永井は勝と一緒に咸臨丸で渡米した使節の一員で、この当時は京都を管轄する幕府の代表でした。
178、「主家に対する忠義ではない。愛国ということです。・・・古来武士は・・・主家あることを知って国家あるを知らなかった、と竜馬は説きつづけた。
忠義は知っているが、日本を愛することは知らない。日本六十余州のみが唯一の世界であるときはそれでよかったし、それでこそ世界に冠たる日本武士道は出来上がった。
しかし今やそれが邪魔になっている。
「赤穂浪士では日本を救えませんぞ」
外国がいる。この島国の周りをぐるりと取り囲み、隙あらば侵略し、属国化しようとしている。日本人が有史以来、初めて国際社会の中の自分というものを、いやおうなく発見させられたのが、今日の状態といえる。
赤穂浪士の映画は師走の一つの風景でしたが、最近は余り流行りませんね。日本人の意識が変わってきています。大石内蔵助といえば、知らぬ者がなかった世代は徐々に社会の中軸をはずれ、年金生活者になってきています。むしろ、後期高齢者でしょうかねぇ。
私を含めて、この人たちの心の中には忠義という価値観が生きていました。赤穂浪士を見るたびに、それを思い出していたのです。戦後「親に孝、君に忠」は否定されましたが、「君」に代わって「会社(役所)に忠」という価値観になりました。会社というのは江戸時代の藩と良く似た性格を持ちます。社長という藩主がいて、重役がいて、管理職という名の上士がいます。そして下士であるヒラクラスがいます。会社が藩士(社員)に求めたのは、英語でごまかしたロイヤリティー(忠義)でした。
主家(会社)あることを知って国家あるを知らなかった。
これが多くの企業戦士たちの生き様でしたよね。
国内市場が飽和し、新たな市場を求めて海外に進出していきました。会社への忠義は知っているが、日本を愛することは知らない。それが、企業戦士の会社人生でした。
日本六十余州のみが唯一の世界であるときはそれでよかったし、それでこそ世界に冠たる日本武士道(日本的経営)は出来上がった。
日本の高度成長期は、まさしく司馬遼太郎が指摘する通りでした。が、バブルの崩壊から時勢が変わりました。忠義は急速に色あせます。リクルートで自分を高く売りつけることが美徳となり、役員報酬は天井知らずのお手盛り相場になって行きました。
外国(企業)がいる まずはアメリカ企業が入ってきました。IBM、Motorola、GM、GE
彼らはアメリカの雇用制度を日本に展開します。ヨーロッパもやってきました。そして、韓国、中国もやってきました。忠義とは縁のない価値観に染まっていきました。国際社会の中の自分というものを、いやおうなく発見させられたのが、今日の状態といえる。
そうです。それが現代なのです。
歴史とは、こうやって読むものではないでしょうか。「学べば学ぶほどわかった」前総理の迷言は、あながち迷言ではなく、現代に生きる日本人の実感かもしれません。
しかし、問題が起きる前に学んでおくのが勉強の本筋です。ぶっつけ本番、それで凌ぎきれるような人格者はなかなかいないのが現代でもあります。
179、後藤は例の面(つら)つきで頷き、パークスに向かって「まず聞きたい」といった。
「当初我々は、貴官が交渉の目的でこの土佐にやってくると伺っていたが、どうやらそうではないらしい。いやしくも拙者は使臣である。それを前にお手前の無礼、凶暴の態度はどうであろう。されば目的は交渉ではなく挑戦と見た。挑戦ならばこれ以上拙者がここで座っているのは無用である。談判の中止を希望する」
長崎で英国水兵殺傷事件が起きます。
パークスは得意の脅迫外交で土佐藩を脅します。オーバーアクションを次々に繰り出し、これでもか、これでもかと土佐藩に法外な要求を突きつけます。
が、英語が全くわからないというのが後藤の強みでした。通訳のアーネスト・サトウが日本語に通訳するまで、後藤象二郎はイングリッシュ・ダンスを観劇していたのです。
私にも経験がありますが、欧米人は、まず自己主張からはじめます。理路整然と間違ったことを、臆面もなく主張します。これが、彼らの言うディベート・テクニックです。
なまじ、英語がわかると反論したくなり、反論すると、彼らの術中にはまります。その意味では英語の苦手な文聞亭は幸運でしたが、多くの日本人ビジネスマンは「君は英語が出来るから…」とおだてられて海外ビジネスに参加していきました。幕府の外国奉行に任命された人たちと変わることはありません。術中に嵌り(はまり)、不平等条約に調印することになります。最近では中国語でしょうか。にわか仕込みの中国語で罠に嵌ります。
後藤象二郎の態度は間違いなく正解で、Here is Japan. You must speak Japaneseと言ってやればよいのです。日本で商売したかったら、日本語くらい勉強してくるのが当然です。
特にアメリカ人が傲慢ですね。「こんにちは」「ありがとう」の最低限の日本語すら知らずに来る奴が多すぎます。が、それを許す日本人も馬鹿ですねぇ。幕府の外国奉行を笑えませんよ。尖閣列島事件での政府の迷走を笑えませんよ。
この対応には、通訳をしていたアーネスト・サトウが慌てます。今まで出会ったことのない日本人でした。日本人と言えば「脅せば黙る、謝る」がすべてで、パークスの無礼を指摘されたことなど一度もなかったのです。
サトウは後藤の言葉を通訳せずに、パークスに耳打ちします。
「パークスさん、こいつはいつもの日本人じゃぁない。ジェントルマンに戻った方がよい」
パークスは、自分が道化師を演じていたことを知って、うろたえます。交渉の全権をサトウに任せて、逃げ出してしまいました。
アーネスト・サトウ…日系英国人と思われる方がいらっしゃると思いますが、由緒正しきスコットランド人です。サトウは、維新後も日本に留まり、維新政府のアドバイザー的な役割を果たします。同様な英国系人物として倉場(グラバー)富三郎がいますが、彼はグラバーとお鶴の間に生まれた息子で、岩崎弥太郎の片腕として活躍します。
180、幕府としてはこれだけ騒いでこのまま審議打ち切りでは威信にかかわるため、 奇妙な結審方法を考え出した。「恐れ入れ」というのである。
竜馬は証人の資格で別室にいたが「悪くもないのに恐れ入れるか」と鼻で笑った。
岩崎弥太郎は恐れ入ったが、菅野は最後まで恐れ入らない。ついに奉行が折れて、「お構いなし」に判決を変え、無罪放免になった。
英国水兵殺傷事件は、結局、犯人不明のため迷宮入りします。佐幕派の土佐を脅して、フランス寄りの幕府に打撃を与えようとしたパークスの作戦は失敗し、彼は横浜に引き上げてしまいます。まぁ「ちょっとミスったな」程度の感覚です。
が、長崎奉行所は恐慌状態に陥っています。やり損なったら切腹者が何人出るのか…恐怖のどん底です。犯人をでっち上げてでも決着をつけなくてはいけません。
最近冤罪事件が多く、検察の焦り、虚構が暴露されるケースが多いのですが、その、もともとの理由は初動捜査ミスと、思い込みが原因でしょうね。現場の警察官、刑事が見込み捜査をしてしまうのです。しかも、思い込みにはマスコミの報道が悪さをします。探偵を気取った記者たちが、「自主捜査に寄れば…」などと、いい加減な情報、噂をばら撒きます。これに左右されて肝心な証拠を取りそこなうのです。さらに、マスコミは自分の捜査を絶対と信じて、それに逆らう警察、検察を叩きます。彼らは言論の自由を標榜し、一方の警察は守秘義務に縛られますから、広報合戦では勝負になりません。マスコミの横暴…ミニコミの筆者もその一人ですが、反省すべきでしょうね(笑)
事件の真相は…犯人は黒田藩の長崎駐在員でした。「酒は飲め飲め飲むならば、日本一のこの槍を…」と丸山の花街で浮かれた帰り道、町人に乱暴をする英国水兵に腹を立て、バッサリ斬ってしまいました。事の重大さに驚き、犯人は切腹、黒田藩はそのことを隠匿して逃げてしまいました。結果的には、それが日本のために良かったのですが、黒田節も黒田武士も不名誉な歴史を残しましたね。後藤又兵衛が泣いたと思いますよ。